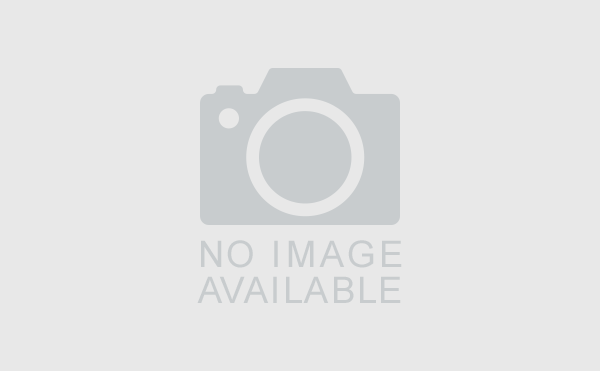関西風お好み焼きについて

お好み焼きの歴史

現代ではボリューム満点の主食として食べられているお好み焼きですが、実は茶菓子として作られたことがお好み焼きの始まりです。お茶で有名な千利休が安土桃山時代に作らせていた、小麦粉の生地に味噌を包んで作る麩の焼きが起源でした。
そこから味噌ではなく餡が包まれた助惣焼が生まれて屋台などで販売されるようになりました。この助惣焼はお好み焼きだけでなくどら焼きの元祖とも言われています。明治時代には東京で今のお好み焼きに近いもんじゃ焼きやどんどん焼きが誕生しています。
戦後の空腹をしのぐために作られたお好み焼き

戦後は小麦粉の配給が多かったため、お米の代わりに小麦粉を使用して作られる料理が普及しました。大正時代から駄菓子屋などで販売されていた一銭洋食をベースにして、キャベツや麺を重ねて腹持ちが良いお好み焼きが作られました。
一銭洋食とは小麦粉を水で溶いた生地を鉄板に薄く伸ばし、ネギなどの野菜を乗せてから半分に折って焼いたものです。一銭洋食自体は子供のおやつ程度のボリュームだったのが、具材を増やすことによって立派な主食になりました。
戦後の厳しい毎日を生き延びるために試行錯誤して作られたお好み焼きは、今や全国各地でたくさんの人のお腹を満たしてくれる人気フードになっています。
お好み焼きの特徴

お好み焼きは刻んだキャベツがたっぷり入っているため野菜もとれて栄養満点です。具のアレンジがしやすいため、一口にお好み焼きと言ってもねぎ焼きや海鮮焼きなど様々な種類があります。小麦粉の生地に具材をたくさんいれて鉄板の上で丸く焼き上げます。みんなで鉄板を囲みながらそれぞれの種類を食べ比べするのも楽しいですよ。
生地

関西風お好み焼きの生地は、カツオだし、小麦粉、卵、そしてすり下ろした長芋を入れて混ぜ合わせます。長芋を入れることにより、生地がふっくらもちもちになります。そして、刻んだキャベツをたっぷり、ネギや紅生姜の薬味を入れます。
具材

関西のお好み焼きに欠かせないのは豚バラ肉です。あとは好みで海鮮を入れたり、餅チーズ、中華麺やうどんを間に挟むとボリューム満点のお好み焼きが出来上がります。
ソース

お好み焼きに使われるソースはとろりと絡みやすい濃厚ソースです。関西風お好み焼きは甘めのソースが主流です。
焼き方

キャベツを荒く刻んで、青ネギは小口切りにします。カツオだし、卵、小麦粉、すり下ろした長芋を混ぜ合わせ、キャベツとネギ、生姜、天かすを入れてまた混ぜます。

鉄板に油をひいて生地を丸く広げます。この時間に麺や具材を入れる場合は生地の間に挟み、上に豚バラを敷きます。生の豚バラを乗せることで豚の油が生地に染みて出来上がりが香ばしくなります。

5分経って生地が固まってきたらコテを使ってひっくり返します。低い位置で一気にクルッとひっくり返すと上手くいきやすいです。

両面焼けたらソース、マヨネーズ、青のり、鰹節でトッピングしたら美味しいお好み焼きの完成です。